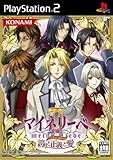読書が好きなんですが、家の本棚が大きくないので、読み終わった本は基本売りに出すことにしてます。残す本はよほどのお気に入りだけ。
その分、読書記録はこまめに取ってます。本の内容を忘れるままはにするのはもったいないし、能動的読書で、読書効果がちょっとでも上がれば嬉しい。あとで感想を振り返ったとき、何か気づきが得られたら儲けものですし。
読書感想のまとめ方は少しずつ変わっていって、はじめは読書メーター、Evernote、マインドマップ(アプリ)。デジタルからアナログな読書感想ノートに転向し、Ca.Crea A4×1/3、ほぼ日手帳、本よむEDiT。現在は、読書記録しおり(+測量野帳)です。この間約8年、大分試行錯誤を重ねてる感じですが、飽きっぽく同じやり方は続かないのでちょうどいいかも。
そんな自分の、読書感想ノートの作り方について変遷語り。読書感想のまとめ方オススメ紹介ではなく、失敗談気味の内容です。
![読書感想ノート]()
はじまりは「読書メーター」。
はじまりは「読書メーター」でした。
読書メーター
読書メーターは読んだページ数や冊数などの読書量をグラフにしたり、 日本中の読書家さんとコミュニケーションできるサービスです。
当時好きだったWebサイト管理人さんが読書メーターを使ってたんですよね。存在を知って「こんな便利なサービスがあるのか!」と自分も読んだ本の感想を投稿するように。誰かから「ナイス!」(いいね!のようなもの)されると嬉しくて。
途中、デザインが垢抜けていて企画や機能が豊富なWeb本棚サービス「ブクログ」に浮気しつつ、
ブクログ - web本棚サービス
結局は読書メーターに戻ったり。読書メーターの方が比較的交流が盛んで「読まれている」感があるので、続けるモチベーションになりやすいんですよね。マイペースに読んだ本の感想を登録しつつ、他の読書家さんの感想を参考に本を買いながら、かなり長く続いた記憶があります。
それからしばらく「Evernote」な日々。
じゃあなんで読書メーター続かなかったの?てことなんですが、きっかけは同時期に利用していたWeb日記サービスが終わったことです。「サービスが終わればデータは消える」という当たり前の事実に気づいたんですよ。それで、本の感想は自分で管理できる場所に置きたいなと。
あと、読書メーターやブクログは他の読書家さんの感想が読めるので引きずられちゃうんですよね、先入観が入りやすい環境というか。
いくつかサービスを比較して、最終的に本の感想を置く場所としたのが、思いついたことを何でも記録できるWebサービス「Evernote」。
思いついたことを簡単に記録できます。 | Evernote
Evernoteのサービスがいつか終わるとしても、エクスポート機能でバックアップを取って、データを逃せると思ったのが決め手です。スマートフォンアプリの導入が早くて、いつでもどこでも書けて読めるのもお気に入りポイント。情報のコピー&ペーストやタグ付けも簡単にできます。
読書感想は「本のタイトル/著者」「概要」「感想」をテキスト形式でまとめていく単純な方法でした。こんな感じ。
![Evernote]()
![Evernote]()
読書メーターは必要事項をWebサービスに登録する感じだったので、読書感想ノートとして意識して書きはじめたのはこの頃かも。初期の頃は書く内容が安定しなくて、ファイルによって文章量もバラバラでしたが、次第にテンプレ化が進み...やがて飽きました。慣れて機械作業になったというか。
「マインドマップ」で連想ゲームな読書記録。
一時期マインドマップにハマってました。自分の考えをまとめたり、勉強でキーワードを整理するのにちょうど良いんですよね。当時も現在も、マインドマップのiPhone/iPadアプリ「SimpleMind」を愛用してます。Dropbox経由のクラウド管理で、出先のiPhoneからでも、家のPCからでも書いたり閲覧したりができて便利。
色んな情報をマインドマップ的にまとめているうちに、読書感想の記録もマインドマップで取るようになったんですよね。記録はこんな感じでつけてました。
![SimpleMind]()
キーワードを繋げていく書き方なので、文章化よりまとめに時間がかかりません。マインドマップの中心から「読了日」「作者名/関連作品」「本の概要」「自分の感想」を枝として伸ばしキーワードを繋げていく方法。頭の整理にもなりつつ、連想ゲームで思いがけない発想が出てきたりするのが楽しい。
ただ、マインドマップで読書記録は、後から読み返した時、何が心に残ったのか、考えていたのか思い出しづらい、かなー。情報が分散しすぎるというか。結局この読書記録法は、マインドマップのマイブームとともに続きませんでした。
マイ・ベスト・ノート「Ca.Crea A4×1/3」。
あるとき奥野宣之氏の本「情報は1冊のノートにまとめなさい」に影響を受け、普段持ち歩いているノートに読書感想の記録も統合することに決めました。使用するのは、A4ヨコ1/3という絶妙なサイズ感で今も昔も愛用している「Ca.Crea A4×1/3」。
![カクリエ]()
1ページにちょうど1冊分、「本のタイトル/著書」「概要」「感想」をまとめていく形です。これまではPCのキーボードをカタカタ、スマホをフリック入力で文字を入力していたのが、紙のノートに手で文字を書いていく感覚がやたら新鮮で楽しく。ここから、読書感想記録がアナログからデジタルになりましたねー。
アナログなノートは意外にも検索性が良くて、ページをペラペラとめくると大体どこに何を書いたかわかります。情報の一卵性も高いし。デメリットは物理的な保管場所な、リングノートなのでちょっと嵩張る。
文房具好きが一度は通る「ほぼ日手帳」の道。
「ほぼ日手帳」を買いまして。というか、ほぼ日手帳歴は長めですが、日記帳のように毎日手帳を書く習慣がなくて、白紙ページの方が多かったんですよ自分の場合。でもあるとき、誰かのツイッターかインスタグラムだったかな、ほぼ日手帳にイラスト付きで書いたカラフルな読書日記の写真を見かけて「いいな真似したい!」と。絵心がないので、文字ばかりですが。
![ほぼ日手帳]()
毎日持ち歩く手帳に読書感想を書くメリットは、隙間時間に読み返す機会があることですかねー。この頃書いた本の感想は、他の時期に書いた本の感想よりよく覚えてる。逆にデメリットは、他の人の目に入る機会があることです。専門書や、百歩譲ってビジネス書の類ならいいんですが、ベストセラーな自己啓発書はなんだか恥ずかしい。
あと、さすがにほぼ日手帳は書くスペースがちょっと小さい。見開き1ページで1冊の感想、くらいでいい塩梅になってました。
本好きっぽいアイテム「本よむEDiT」。
あるとき文房具店で見かけて、マークス社の「本よむEDiT」を買いました。いかにも本好きっぽい読書アイテムだと思いません?持ってるだけでテンションが上がります。クロス貼ハードカバーで、程よい高級感。
![本よむEDiT]()
ちなみにこんな感じで使ってました。フリクションボールとの相性が凄く良くて、消しても跡が残らない。
![本よむEDiT]()
ブックジャーナルページは、本の概要、感想、キーワード/引用に分かれてます。他に、読書リストやお店リストのページもついています。自分はブックジャーナルのページ以外使わなかったけれど。
使い勝手としては、感想とキーワード/引用は逆だと良かったかなー。本の内容をまとめてから自分の感想を書きたい派なので。
残念ながら、これは2冊使って現役引退でした。お気に入りではあったんですが、漫画やエッセイの感想を気軽に書ける価格帯(1600円(税抜き))のノートでないのが続かなかった要因ですかね...。
サイズが四六判で、感想を書く本によってはスペースが余って勿体なさあった。
現在の定番「読書記録しおり」。
学校の図書館、本の裏表紙についていた本の貸出カードあるじゃないですか。現在は、それによく似たBeahouseの「読書記録しおり ワタシ文庫」を愛用しています。
![読書記録しおり]()
紙はケナフ100GAを使用で、油性・水性・ゲルインクのボールペン、万年筆などでも滲むことなく書き込めます。少しざらついた柔らかな風合いが、いかにも貸出カードっぽくていい。ノスタルジーな紙のリーディングログ。
価格も1パック450円(税抜き)でお手頃。1パックで読書記録しおりが3つと専用ノリ付封筒がついてくるんですが、専用封筒は図書館用品メーカー伊藤伊さんのノリ付きブックポケットで、これも本物の貸出カードっぽさを演出してます。レトロだ...!
![読書記録しおり]()
書き込む項目もシンプル&コンパクトで「読始日」「読終日」「本のタイトル」「著者名」「一言感想」のみ。
最初は、読んだ本の感想だけ書いていたんですが、途中から、買った本はすべからく記録するようになり、積ん読本管理もこれひとつでするようになりました。
最新の読書記録しおりだけ持ち歩いて、あとは家で保管しているんですが、たまに古い読書記録しおりを読み返すと、アルバムみたいで楽しい。買ったことすら忘れていた積ん読本の存在に気がついて、ちょっと得した気分に。
もちろん、今までの読書感想ノートほど分量ある感想は書けないので、書きたいなと思った時は本よむEDiTを引っ張り出して書いてます。たまにがっつり読書感想まとめると、それはまた新鮮で楽しくなる。
Web小説感想ログとして「測量野帳&読書感想スタンプ」。
小説家になろうで連載中の作品を読んで感想書いて、やがて作家さんがデビューするまでを見守るのが趣味のひとつでもあるんですが(アイドルがメジャーデビューするまでを見守るのに近い心理)、これも読書記録つけておきたいなーと思い始めまして。小説家になろうのアカウントを持っていればブックマーク機能もあるんですが、やや一覧性に欠けるんですよね。やっぱり情報の一覧性はアナログが向いている。
かといって、読書記録しおりにまとめて書いちゃうと、ちょっと情報レベルが揃っていないのが気になる。紙の本は1冊単位ですけれど、小説家になろうだと短編や連載が同じように載っているので、情報レベルに違いがあるんですね。
というわけで、新たなリーディングログを模索して行き着いたのが、「測量野帳&読書感想スタンプ」という組み合わせです。丈夫で比較的安価、コスパの大変よろしいことで有名なコクヨの測量野帳に、OSANPO Shoppingで購入した読書感想スタンプをペタペタと押して、お気軽読書記録。
![測量野帳&読書感想スタンプ]()
測量野帳って薄いので、次の冊子に映るタイミングが早くて、コンスタントな達成感が得られます。やっぱり「使い切った!」て感覚ってモチベーションにはとても有効。
時には浮気して別の読書記録アイテムに手を出してみたり。
そんなわけで今はほぼ、読書記録しおり(+測量野帳)体制なんですが、何せ浮気性なままで、新しい読書感想ノートやスマホアプリなんかが始まるとつい試しちゃいます。
ちょっと前だと、レトロ購買部ぷに子さんの「図書貸出カード」とか。名刺入れに入るコンパクトサイズで、このチマっと感はとても可愛い。
![レトロ購買部の図書貸出カード]()
あとは、キングジムの「暮らしのキロク」シリーズのBOOKもちょっと手を出してみました。手帳に貼れるふせんタイプ。色々なフォーマットがある暮らしのキロクですが、BOOKは図書カードを意識したフォーマットでレトロかわいいんですよね。
![暮らしのキロク]()
東京は蔵前にある文房具店「カキモリ」ではオリジナルノートをカスタマイズできるんですが、あるとき衝動的に「オリジナルの読書感想ノートが欲しい!」と作ってしまったり。でもこれは勿体無くてまだ使っていない。たまに引き出しから出してはニヤニヤ眺めてる。
![カキモリのオリジナルノート]()
最近は、グリーンハウスの「watashi lassic」シリーズとして発売されたジャーナルノートも気になってます。A6サイズのコンパクトなノートで、320円(税抜き)とお買い得。デザインも可愛くてちょっと欲しい。自重しているけれど。
試した読書感想の記録だけでも10近くあって、どれだけ飽きっぽいんだよ、て感じですが、本の感想を書いて読み返すこと自体も趣味のひとつな気がしているので、もうそれでいいかなーと。
たまに、Evernoteに残したログを読み返すんですが、当時何を読んでいたかや何を思っていたかを読むと、ちょっと黒歴史で恥ずかしい。自分の読書変遷を追っかけてみると、時期によって傾向があったりして楽しい。やたら古典にはまっている時期とか、歴史小説を読み続けている時期とかあります。最近のブームは食べ物エッセイですね。食べ歩きレポっぽいやつじゃなくて、料理を作る過程が文章だけで語られている奴が好み。
そんな感じで読書感想ノートの記録はこれからも続きます。
関連記事
























![ノンデザイナーズ・デザインブック [第4版] ノンデザイナーズ・デザインブック [第4版]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51OV7VCefgL._SL160_.jpg)















































 【CAFE PAPIER】
【CAFE PAPIER】