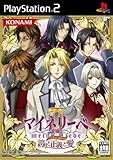小説家になろうの月間ランキングでは長らく「悪役令嬢モノ」がブーム。いつの間にやら大流行り、女性向け恋愛モノとしては一大ジャンルになってます。
悪役令嬢モノというのは「前世でプレイした"乙女ゲーム"or愛読していた"少女マンガ"の世界に転生した主人公が、自分は"ヒロインをいじめる悪役"のポジションだと気がつき、シナリオで予定されたバットエンドを回避するため東奔西走する」系ジャンル。
それ以前、女性向けでは「乙女ゲーム世界に脇役(モブ)転生して傍観生活」がブームでしたが(詳しくはなろう女性向けのブーム変遷)、大分能動的になった印象です。傍観系脇役だとやはりストーリー展開しづらいんですかねー。
悪役令嬢モノは、既定の物語に干渉して運命を捩じ曲げる、カタルシス的な要素が読者にウケた気がします。局地的に流行った「ざまぁ」展開(実は腹黒な良い子ちゃんヒロインに陥れられた、悪役ポジションの主人公がヒロインの化けの皮を剥いで「ざまぁwww」と笑う展開)とか、カタルシスを生むお手本のような流れでしたし。
悪役令嬢モノの有名どころとしては、やることなすこと悪い方向に解釈される伯爵令嬢が主人公の「悪役令嬢後宮物語」(ただしこれは転生ではない)や、
乙女ゲームの悪役に転生した少女が、ゲームシナリオの悲劇が起こらないようフラグ回避を試みる「ヤンデレ系乙女ゲーの世界に転生してしまったようです」などが書籍化。
その後も悪役令嬢モノの書籍化は続き、すでに両手の指では足りない数の悪役令嬢モノが商業作品として世に出ています。
それで、悪役令嬢モノ。これほど流行ると、ランキングで見かけるたび「悪役令嬢のネタ元、ルーツって何だっけ?」と疑問が頭をよぎるので、悪役令嬢の歴史・ルーツを、漫画やゲームから考察したのがこの記事です。
ちなみに、小説家になろう内の悪役令嬢ものブーム変遷について考察した記事はこちら(「悪役令嬢モノ」のブーム変遷)。
そもそも悪役令嬢って何?
まずは定義から。悪役令嬢は、ヒロインの成長を促したり、ヒロインに対する読者の同情を誘ったりするための敵役、ライバル役です。要素としては、
- 相手を服従させる権力を持つ(例:王族や政治家といった権力者。貴族、富豪の娘といった金持ち)
- 相手を納得させる権威を持つ(例:王族、貴族の血筋といった身分・階級。ヒーローの婚約者、何らかジャンルの実力者、学園モノなら生徒会役員といった地位)
- ヒーローに恋してるand/orヒロインを嫌ってる。
- 展開によって「ヒロインの無二の親友」or「ヒロインの永遠のライバル」or「退場(社会的な死)」の3つのルートが存在。小説になろうでは退場が多く、これを回避するために悪役令嬢が奔走
4のメタ思考(お約束)は横に置くとしても、1はヒロインを苛めても周囲に制止されないくらいの権力がないと話にならないですし、2は悪役令嬢たるもの取り巻き、腰巾着くらいいないと悪の華として見栄えがしません。3のヒロインを苛める理由がないと、苛め自体発生しませんし。そう、悪役令嬢は、陰日向とヒロインを苛めないといけないのです。
ドラマで例えると典型的なのが「家なき子2」の木崎絵里花(役:榎本加奈子)。一条財閥のお嬢様で、黒髪ストレートのぶりっ子系、ヒーローに恋してヒロインを嫌い、最後はヒロインの友人に下剋上されて退場します。
史実では、令嬢でなく王妃ですが、フランス国王ルイ16世の王妃マリー・アントワネットでしょうか。「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」の台詞は、いかにも悪女っぽい。ラストがギロチン処刑というのも、小説家になろうの悪役令嬢への影響は大きそうです。ただ、フランス革命下という時代背景的に連想される「ベルサイユのばら」(池田理代子)(1972年)では、アントワネットはむしろヒロインポジションにいます。
ちなみに、お嬢様というと連想されがちな「アタックNo.1」(浦野千賀子)(1968年)の早川みどりや「エースをねらえ!」(山本鈴美香)(1973年)のお蝶夫人、「ガラスの仮面」(美内すずえ)(1976年)の亜弓さんみたいな人たちは、ヒロインと衝突はしつつも苛めてはないので、ただのお嬢様ライバルキャラです。
...見た目的影響はあるかも知れませんが。たてロールの髪型とか、ツリ目がちの整った顔立ちとか、ですわ口調とか。取り巻きも多いですしね。
少女マンガの悪役令嬢を探します。
悪役令嬢のイメージをなんとなく掴んだところで、少女漫画の悪役令嬢を探していきます。
60年代
ヒロインを苛めるお嬢様、というと、古くは60年代から。
「ガラスの城」のあらすじは「イサドラは母の死の間際、妹のマリサ(ヒロイン)が実は伯爵令嬢であることを知る。マリサに成り代わって令嬢となるイサドラ。イサドラはマリサのことを召使として側に置き、苛め抜く」というもの。
成り代わりではあるものの、美少女なイサドラはいかにもお嬢様で、ヒロイン苛めっぷりが半端ないです。ただしヒーロー不在。主人公を憎んでるタイプですね。
成り代わり令嬢がヒロインを苛める(というか命を狙う)展開は「伯爵令嬢」(細川智栄子あんど芙〜みん)(1979年)でもあります。宝塚で上演されたのでこっちが有名かな。記憶を失った少女コリンヌ、元スリで成り代わり令嬢となったアンナ、ふたりの貴族青年による四角関係が、ベタすぎて逆に新鮮。
70年代
もう少し時代が進んで70年代、といえば、世界的にも有名ですね、
「明るく前向きな孤児の少女キャンディ(ヒロイン)が、周囲の偏見に負けずに人々に影響を与え成長していく」ストーリー。キャンディを苛める令嬢でイライザが序盤から登場。
兄のニールと一緒にヒロインを苛めるイライザはとっても悪役なお嬢様です。何より縦ロール。マンガの知名度的にも悪役令嬢の原型はイライザ、という人が多いんじゃないかな(主人公の幼馴染で貴族の養女になり、微妙に距離を置くようになったアニーの方が腹黒令嬢扱いされることも。恋敵だしね)
同じ70年代、「王家の紋章」(細川智栄子あんど芙〜みん)(1977年)では、ヒロインのキャロルをヒーローの異母姉であるアイシスが執拗に命を狙ったり、「ときめきトゥナイト」(池野恋)(1982年)で、ヒロイン蘭世にライバル曜子お嬢さんがヒーローを巡って恋の鞘当てをしたり。曜子さんは、暴力団組長の娘設定なので、ちょっと違うかなー。
前述の「ベルサイユのばら」もこの時代。ポリニャック伯夫人やジャンヌ、デュ・バリー夫人はポジション的にまさに!かも。
悪役令嬢と関係ありませんが、この時期、少女漫画の神様とも呼ばれた萩尾望都先生が「ポーの一族」を連載されてます。キャンディ・キャンディ、ベルサイユのばら、ポーの一族...こう並べてみると伝説的な時代だ。
80年代
さらに時代を進めて80年代。お金持ち学校を舞台にした「有閑倶楽部」(一条ゆかり)(1981年)や「笑う大天使」(川原泉)(1987年)なんか有名で、真性お嬢様おぼっちゃま出てきますが、あれ、サスペンスやコメディでジャンル違いだと思うので割愛しました。でも「舞台設定:お金持ち学校」という意味で、有閑倶楽部の影響は大きいはず。
90年代
次の90年代。漫画からドラマ・映画・アニメなど多角的に展開されたので、普通に男性だって名前を知ってるかと思います。
「お金持ち学校が舞台+庶民ヒロインが苛められ、やがて周囲に認められていく」という王道展開は、昨今の悪役令嬢モノの原典に上げる人が一番多そうな作品。庶民ヒロインつくしちゃんを苛めるリリーズ(百合子さまと仲間たち)がいます。
小説家になろうで「ジャンル:悪役令嬢」のブームの発祥になった、ひよこのケーキ先生の「謙虚、堅実をモットーに生きております!」作中作マンガ「君は僕のドルチェ」は、「花より男子」オマージュぽいですよね。若葉ちゃんと鏑木の関係性が、往年のつくしちゃんと道明寺に被る人、結構いるんじゃないかな。まぁでも花より男子には、麗華さま的強力なライバルキャラは登場しないですが。
00年代
そしてその先00年代ミレニアム。
空前の執事ブーム到来。やっぱり榮倉奈々、水嶋ヒロ、佐藤健競演で話題になったメイちゃんの執事が飛び抜けて有名なんでないかと。主人公メイちゃんに対するライバル役で詩織様がそんな立ち位置です。
同じようなお嬢様学校+庶民ヒロイン+オプション執事だと「執事さまのお気に入り」(津山冬、伊沢玲)(2007年)もあります。
これ以降、2010年代以降も悪役令嬢的なポジションのキャラクターは随所に出てきますが、すでにオリジナルを前提とした、ある意味アイコン(記号)としての悪役令嬢という印象です。少なくとも源流とはいえないかと。
こうした悪役令嬢的なポジションのキャラクターは、少女マンガに限らず、少年マンガや青年マンガにも時折登場しています。男性向けの場合は、ツンデレ要素をつけて準ヒロインなことも多いですねー。
乙女ゲーの悪役令嬢はマイネリーベにあり。
初代乙女ゲーム「アンジェリーク」(1994年)の時代から、ロザリアのようなお嬢様キャラは登場してます。乙女ゲーム2作目の「アルバレアの乙女」(1997年)のファナもお嬢様キャラ。いずれも切磋琢磨が気持ちよい、お嬢様ライバルキャラです。女王や聖乙女の地位を巡って、苛めなんてせず正々堂々ヒロインと戦ってくれます。
その後、「ときめきメモリアル Girl's Side」(2002年)の須藤さんや 「ワンド オブ フォーチュン」(2009年)のシンシアなど、ヒーローを巡る恋の鞘当て的お嬢様キャラが出てきますが、正直、登場時間的尺の短さから存在感が薄い。ほら、乙女ゲームって、マルチシナリオで複数ヒーローそれぞれにルートがあって、そのうちひとりのライバル役でしかないので…。
でもそんな中、燦然と悪役令嬢が登場した乙女ゲームがありました。
明るく家庭的な成金お嬢様、ぶりっ子腹黒公爵令嬢、男勝りクールお嬢様が、ヒーローを巡ってヒロインとつばぜり合いを繰り広げるゲーム。「ジャンル:美少年誘惑シュミレーション」の名は伊達ではなく、油断するとヒロインは陥れられます。
悪い噂を流されるのは序の口で、ヒロインがうかうかしてると媚薬でヒーローを奪われる、という屈辱を味わうのですよ…!!でも、攻略対象を玉の輿に乗る手段としか思ってない感じの潔さが、一部女子から圧倒的支持を受けました。ヒロインも俄然強めで、手紙に小細工したり、誘いを断るライバルを「使えないヤツ」と毒づいたり。
ちなみにamazon絵はⅡの方です。学園に中途編入したと思ったヒロインがいきなり卒業式でヒーロー役が起こしたクーデーターに巻き込まれ、革命側か中立かレジスタンス側かを選ぶと言う。「え、私は乙女ゲーをやってるんだよね!?」と思いながらミニゲームで鉄橋の爆弾処理をしました。
また、アンジェリーク、アルバレアの乙女に次いで乙女ゲームの黎明期を飾った「ファンタスティック・フォーチュン」(1998年)、一部攻略キャラのルートのみ登場する貴族令嬢ミリエールが、暗躍する悪役令嬢です。 こっちはちょっとイレギュラーで、ヒーローを憎んでる系。
そういえばミリエースも縦巻きロール(ポニーテールですが)なので、この時はすでに縦巻きロールが悪役令嬢アイコンになってたってことなんでしょーか。まぁ乙女ゲームの歴史自体、少女マンガに比べれば圧倒的に遅いですしね。少女マンガから輸入されたと考えるのが妥当なのかな。
余談。少女小説の悪役令嬢を求めて。
小説家になろうの悪役令嬢モノでは、前世で見た"ゲーム"か"少女漫画"をベースにすることが多いため、言及は少ないですが、少女小説、ライトノベルにも悪役令嬢っていそうですよね。少し調べて見ました...というか記憶を辿りました。
古くからある少女小説、コバルト文庫でお嬢様が登場する小説として有名なのは、久美沙織先生の「丘の上のミッキー」(1984年)。ただし、ライバルお嬢様はいても悪役令嬢的な立場の人がいたかというと...?むしろ、藤本ひとみ先生の「漫画家マリナシリーズ」(1985年)の方が、過激で意地悪な女性をよく登場させていた記憶です。
少女小説で悪役令嬢の源流に近いのは、さらに進んで1991年、学研レモン文庫から出版された森奈津子先生の「お嬢さま」シリーズの方でしょうか。正統派ヒロインよりも、悪役でありたいと自負するお嬢さまを中心にした学園ギャグコメディ。...というか気がついたら復刊されてる...!?
正直、悪役令嬢というからには、貴族社会が舞台になっていないと活躍の場を作るのが難しそうですが、少女小説の主戦場は今も昔も学園のため、馴染みにくさがあるんですよね。舞台設定的に、ハーレクイン小説の方が悪役令嬢はいそう(ハーレクイン詳しくないので想像です)。
そんなわけで総括。
ガラスの城から数えると、なんと半世紀も前から悪役令嬢はいたことに。
これだと正直、作家の青春時代がいつかで、悪役令嬢のルーツは違ってそうです。まぁそもそも、小説家になろうの作家陣自体、年齢層は割と広範囲で、同じ文化・文脈(コンテクスト)を共有していると考えるのは無理があるのかも。
前述の「悪役令嬢後宮物語」や「謙虚、堅実をモットーに生きております!」から影響を受けた(オマージュ)作家が、悪役令嬢のイメージを再生産して、その成功例の幾つかがさらに再生産を重ね、今の小説家になろう的な悪役令嬢のイメージが出来上がった、と考えるのが妥当な気もします。
自分の肌感覚としては、キャンディキャンディのイライザで「悪役令嬢」のイメージが作られ、花より団子やメイちゃんの執事で悪役令嬢が活躍する「お金持ち学校」のイメージができた感じですが、小説家になろうの悪役令嬢モノが初めて見た悪役令嬢だ、て人も少なからずいそうです。
つまり、小説家になろうの悪役令嬢の原型は、たくさんの作家が集合知的に作り上げた、架空のオリジナルって感じですかね。もし「これがオリジナルだ!」てのが他に思い浮かぶ場合は教えてくださいー。
関連記事